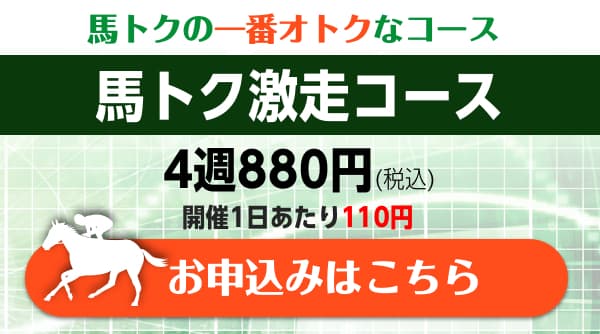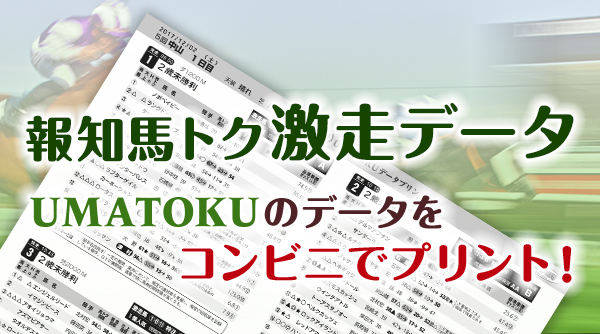11月24日、東京競馬場でG1のジャパンカップが行われた。1981年の創設以来、初めて外国馬の出走がないという特異な状況。国内のトップホースが集っての戦いに、いつも通りの大歓声が起こったが、「世界を知る」という当初のレースの目的を考えると、寂しさは否めなかった。
ジャパンカップの歴史は、一頭の日本馬の果敢なスタートダッシュから始まった。1981年11月22日の記念すべき第1回のレースで、真っ先にゲートを飛び出したピンク色の勝負服。「日の丸特攻隊」と名付けられた快速馬サクラシンゲキと小島太騎手だった。
米国(3頭)、カナダ(3頭)、そしてインド(1頭)から計7頭の外国馬が参戦。日本馬は、天皇賞・秋で1、2着だったホウヨウボーイ、モンテプリンスをエース格に8頭が出走した。「行け!ホウヨウ」―。レース当日のスポーツ紙の一面に躍った見出しは、明確に覚えている。「少年(ボーイ)よ王子(プリンス)よ魂を賭して!」とうたった専門紙もあった。国と国との戦いなら、たとえ日本が格下であっても簡単には負けられない。ファンの愛国心に訴えるようなトーンの紙面が、よりレースを盛り上げた。
1番人気は実績最上位の米国馬ザベリワンだったが、2、3番人気にはモンテプリンスとホウヨウボーイが続いた。サクラシンゲキは12番人気。それでも、勝ち負けとは違う部分で日本の期待を背負っていた。
この馬が参戦する意義。それは、ハナを奪うことにあった。現在、本紙評論家として活躍する小島太さんが振り返る。「外国から速い馬がやって来る。1600メートルでも長いくらいだったが、日本にも負けないスピード馬がいることを見せなければならなかった」
同年2月のスプリンターズステークス(1200メートル)を6馬身差で逃げ切った、典型的な短距離の逃げ馬。それでも、現在のように距離体系が確立されていない時代だったため、進む路線についてはボーダーレスなところがあった。現に、前年の暮れには2500メートルの有馬記念に出走している(結果は10着)。
ゲートが開いた。小島太騎手は、8番枠から手綱を押しながら内側に切り込んで行き、使命を果たすべく先頭に立った。「失格かセーフか、ギリギリの進路取りだった」直後にカナダの先行馬ブライドルパースが続く展開。逃げ脚を緩めることはできない。200メートルごとのラップが10秒5―11秒5―11秒4―11秒7。800メートルまで全て12秒を切るというペースは、今の2400メートルのレースでは、まずあり得ない。
「超」の付くハイラップ。それでもサクラシンゲキは、ラスト200メートル手前まで先頭を譲らなかった。最後に力尽き、後続馬に次々とかわされても、小島太騎手は右ムチを放ち続けた。「中盤以降は、うまく息を入れて思い通りの競馬が出来た。いささかの悔いもないレースだった」。まさに、完全燃焼の9着だった。
優勝は、5番人気の米国牝馬メアジードーツ。コースレコードを1秒も更新し、見る者を驚かせた。演出したのは、もちろんサクラシンゲキだ。「当時、日本で国際レースが開催されるなど、考えもつかなかった。『外国馬に負けるなら仕方ない』と言っていても、心の中には負けたくないという意地があった。本当にワクワクしていたし、いい雰囲気の中で競馬が出来たことを感謝している」と小島さんは言った。
あれから39年。日本の競馬は飛躍的な進歩を遂げた。ジャパンカップを外国馬が敬遠するのは、日本馬が強くなった証(あかし)とも言える。岐路に立たされた国際競走。小島さんが懐かしむ「ワクワク感」を取り戻すため、JRAには大胆な改革を望みたい。(記者コラム・浜木 俊介)