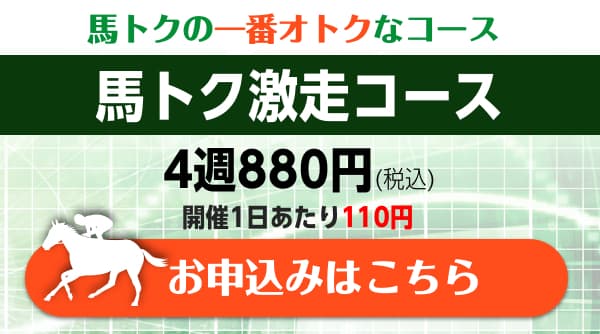◆第9回ジャパンC・G1(1989年11月26日、東京競馬場・芝2400メートル、良) 優勝 ホーリックス(Lオサリバン騎手、ニュージーランド・DJオサリバン厩舎) 2着 オグリキャップ(南井克巳騎手、栗東・瀬戸口勉厩舎) 3着 ペイザバトラー(Cマッキャロン騎手、米国・Rフランケル厩舎)
30年前のジャパンCは刺激的だった。追い切り翌日の東京競馬場出張厩舎。オグリキャップの担当厩務員、池江敏郎が表情を緩めながらつぶやいた。「わし、あの馬が気になるのやけどなあ…」視線の先は小柄な芦毛だった。前年の優勝馬ペイザバトラーでも、凱旋門賞馬キャロルハウスでもない。ひときわ目立つ女性厩務員バネッサ・バリーがブロンドの髪をなびかせながら引き運動していたニュージーランドのホーリックスだった。
過去8年間、白星がなかった南半球勢。実績面で見劣る6歳牝馬の評価は高くなかったが、週末へ向けて注目度は確実に増していた。理由は明快だった。調教では連日のように時計を出していたからだ。長距離空輸、到着後には検疫があり、調整に苦心する外国招待馬が多いなか、この馬は体調面の不安は皆無だった。
日本は天皇賞・秋で1、2着だったスーパークリーク、オグリキャップの二枚看板に、復活へ懸命に調整するイナリワンもいた。当時存在した地方馬の枠は、南関東の女傑ロジータが占めていた。オグリキャップはマイルCSからの連闘策とあって、主役は100回天皇賞馬スーパークリークの方だった。
レースはアメリカのホークスターが主導権を握るとみられていた。直前のオークツリー招待Hで2分22秒8の世界レコードをマークしており、その快速ぶりが注目された。ところが、イギリスのイブンベイが先手を奪う。続くホークスターと2頭が、前半1000メートル58秒5のハイペースでレースを引っ張る。ホーリックスが3番手で、その直後にオグリキャップとスーパークリークが並んで進んでいた。
4コーナー、先行する2頭の間に生まれた1頭分のスペースを、ホーリックスの鞍上ランス・オサリバンは見逃さなかった。直線を向くと、素晴らしい瞬発力で、鉛色の馬体があっという間に抜け出した。刻まれた超絶ラップに、後続馬は追い上げる力が残っていなかった。勝負あり―。誰の目にもそう映ったが、もう一頭の黒い帽子が、ひと呼吸遅れて猛然と飛んできた。
ホーリックスとオグリキャップ。オサリバンの水車ムチか、南井の剛腕か。2頭の芦毛が並んでゴールを迎えたが、栄冠は首差でホーリックスに輝いた。「この馬で好勝負できなければ、南半球のレベルは低い。そう思うしかない」。レース前から期待を隠さなかった関係者の執念が実った。
電光掲示板に浮かび上がった数字に、14万の観衆は驚いた。2分22秒2。ホークスターが来日前にサンタアニタでたたき出した世界レコードが、東京で塗り替えられた。敗者と呼ぶにはあまりにも惜しいレースだったオグリキャップだが、南井、瀬戸口調教師は笑顔で声をそろえた。「同じ2着でも今回は違う」。天皇賞でみせた悔しげな表情はなかった。
表彰式で、ホーリックスの首をなでるバネッサ・バリーの泣き笑い顔が、夕日に輝いて見えた。今年は外国馬の参加がない。今度、こんなシーンが見られるのは、いつなのだろうか。
(吉田哲也)=敬称略=